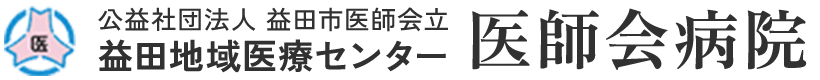Doctor Interview
ケアを通じて患者さまの
暮らしと心に寄り添う
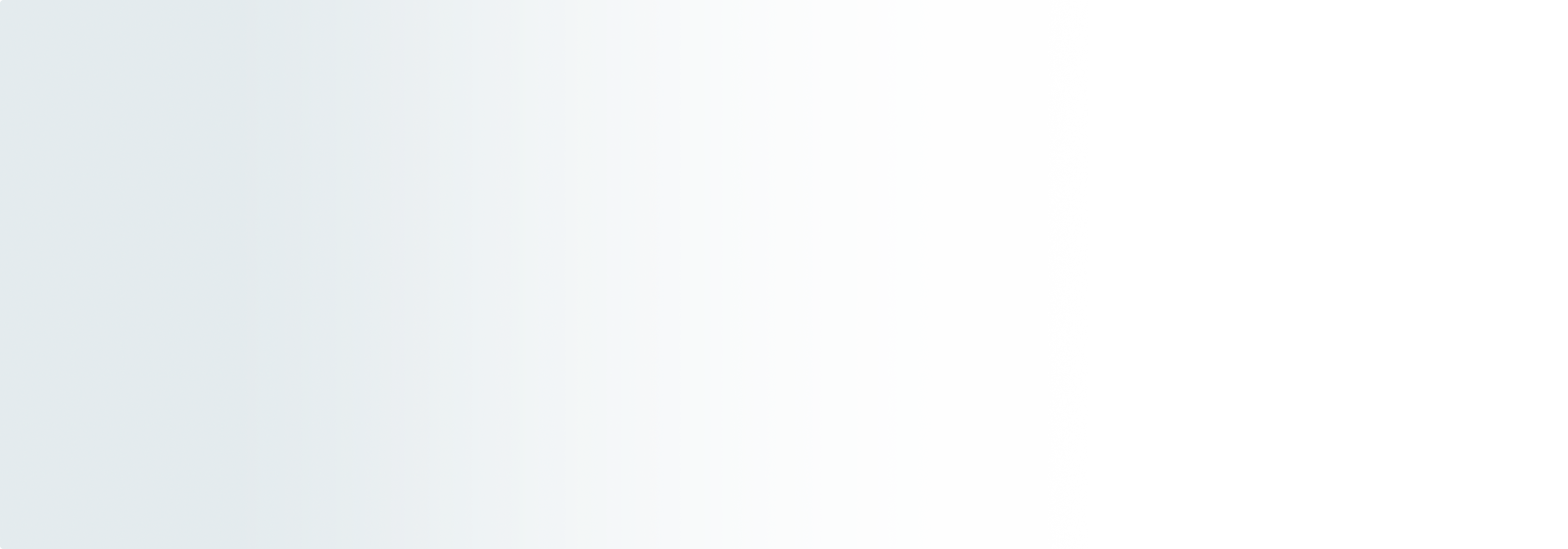

Doctor Interview
ケアを通じて患者さまの
暮らしと心に寄り添う
Interview –漫画に夢中だった幼少期
私は鳥取県米子市で生まれ育ち、高校を卒業する18歳までをそこで過ごしました。その後、島根医科大学(現在の島根大学医学部)に進学し、医師への道を歩み始めました。現在67歳となり、医師として日々充実した時間を過ごしています。 幼少期の私は、漫画という一つの文化に深く魅了されていました。当時、手塚治虫、赤塚不二夫、藤子不二雄といった名だたる漫画家たちが活躍し、漫画雑誌が創成期を迎えた時代でもありました。週刊誌や月刊誌をはじめ、少女漫画誌に至るまで、ジャンルを問わず幅広く読み込んでいました。その情熱は尋常ではなく、貸本屋といった漫画文化を支える場所をフル活用しながら、最新の作品を手に入れる工夫をしていたほどです。
特に印象的だったのは、赤塚不二夫先生が著した「漫画の描き方」という本です。その中で、「物語を作るには起承転結が不可欠であり、映画を観たり落語を聴くことが勉強になる」といった教えに心を打たれました。当時の私は、映画館に通うには少し敷居が高かったため、ラジオやテレビで放送されていた落語を熱心に聴きました。物語の構造や言葉の妙を学ぶ中で、自分の感性を育てる大切な経験になったと思っています。
Interview –麻酔科医としての歩み
医師を志したのは高校2年生の頃でした。「人の役に立ちたい」という漠然とした思いが芽生え、自分の力で完結できる仕事として医師という選択肢が浮かびました。また、当時の社会情勢も私の決断に影響を与えたと思います。
島根大学を卒業後、医局に入局し、関連施設で経験を積みながら麻酔科医としてのキャリアを重ねました。1999年には島根大学の麻酔科教授に就任しましたが、これには私自身の努力だけでなく、タイミングや周囲の後押しが大きく関わっていたと思います。当時の私にとって教授のポストはまだ少し早い挑戦でしたが、次世代を担う責任を果たすために尽力しようと決意しました。教授としての24年間は、非常に充実した時間でした。臨床はもちろん、教育や研究にも力を注ぎ、医師としての仕事だけでなく教育者としての役割も担いました。
2023年4月1日、益田地域医療センター医師会病院の院長に就任し、地域医療のさらなる発展に貢献する立場を担うこととなりました。前任の狩野稔久名誉院長の後を継ぎ、地域住民の健康と暮らしを支える医療体制の構築に努めております。

Interview –救急から麻酔科、そして緩和ケアへ
私自身、最初から麻酔科を目指していたわけではありません。医師になった当初は、救急集中治療に興味があり、全身管理を学んだ後に循環器内科へ進むつもりでした。しかし、麻酔科での修行を続ける中で、その幅広い診療分野に魅了され、キャリアの後半は緩和ケアという新しい分野に力を注ぐようになりました。緩和ケアは、超急性期の治療だけでなく、患者さんの全身を診る視点を持ち、身体的・心理的苦痛を和らげるという麻酔科の理念と一致しており、私にとって非常に意義深いものでした。


Interview –治療だけでなく心や社会的な苦しみにも寄り添う
麻酔科医としての私のライフワークを一言で表すとすれば、それは「ケア」という言葉に集約されます。医療とは、単に病気に対して薬や手術で治療を施すだけではなく、患者さんやそのご家族がより快適に過ごせるようサポートするものであるべきです。その中には、身体の苦痛だけでなく、心の苦しみや社会的な悩みを和らげるという役割も含まれます。こうした苦痛を完全に取り除くことは難しいこともありますが、患者さんがその人らしく暮らせる環境を作ることを目指して、日々取り組んでいます。
緩和ケアは、まさにその「ケア」という概念を中心に据えた分野であり、私にとって医療の原点とも言えます。麻酔科はもともと「ケア」という言葉と深く結びついている診療科です。集中治療のICU(Intensive Care Unit)もその名の通りケアが基盤であり、麻酔にもMonitored Anesthesia Care(MAC)という言葉があります。これはモニタリングを行いながら、患者さんの痛みを和らげたり、眠った状態で安心して治療を受けられるようにするケアの一環です。
近年では、手術室で行われる手術そのものが減少傾向にある一方で、麻酔が必要とされる場面は増え続けています。たとえば、カテーテル治療やTAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)など、手術以外の治療でも麻酔のサポートが欠かせません。患者さんの痛みを取り除き、リラックスした状態で治療を受けていただくために、麻酔科の役割は今後さらに広がっていくと感じています。
Interview –緩和ケアに注力するきっかけとなった生体肝移植の経験
緩和ケアに特に注力するきっかけとなったのは、1989年に担当した世界で4例目、日本初の生体肝移植の経験でした。私はその手術の麻酔と集中治療を専従で担当し、1歳3ヶ月の患児と24時間を共に過ごしました。当時は、生体肝移植が始まるかどうかという医療の大きな転換期でもありました。肝不全や心不全、循環不全といった厳しい状態の中で必死に頑張るその子の姿を見ながら、「この治療が本当にその子自身の望みなのか」という疑問が何度も頭をよぎりました。判断が難しい年齢の患者さんに対し、医療者としてどのように寄り添うべきかを深く考えさせられた経験でした。
手術後、その子が元気を取り戻し、笑顔を見せてくれたときの喜びは今でも鮮明に覚えています。しかし同時に、命を救うための治療の中で、患者さんが抱える心の苦しみや不安をどう支えられるのか、改めて考えるようになりました。治療だけでなく、「その人が何を望んでいるのか」に向き合う姿勢が必要だと感じたのです。
その思いは、2003年の緩和ケアセンター立ち上げに繋がりました。これは日本でも新しい取り組みであり、麻酔科の中で全身管理の一環として緩和ケアを確立するための重要なステップでした。そうした取り組みを推進できたことは、私にとって非常に大きな一歩でした。

Interview –医療とケアの両輪で支える自立支援型の病院
当院が果たすべき役割は、一つの急性期医療をここで完結させることではありません。むしろ、県内外の医療資源と連携し、サテライトとして、または患者さんにとって最も身近な拠点として機能し、患者さんを適切な、サテライトとして、またはファーストタッチの拠点として機能し、患者さんを適切な医療機関へつなげる橋渡し役を担うことが重要だと考えています。 特に、益田市や保健所、近隣の医療機関と協力し、地域全体で高度医療と地域医療をつなぐ仕組みを作ることに注力しています。どこで暮らしていても、たとえば島根県内の松江や出雲といった地域に住んでいても、安心して高度な医療を受けられる体制を整えることが大切だと考えています。
さらに、地域包括ケアを実践する病院としての機能も重要です。益田地域では40%近い高齢化率を背景に、急性期治療を終えた患者さんが、可能な限り早く自宅に戻り、自分らしい生活を取り戻せるよう支援することが求められています。これは単に健康を守るだけではなく、リハビリや栄養指導、口腔ケアといった生活の質を向上させる取り組みを含めた多角的な支援を意味します。
私たちは、このような包括的なケアを提供できる「支える土台」をすでに備えていると考えています。地元の開業医の先生方と連携し、介護施設や在宅医療の支援体制を整えることで、患者さんの生活を総合的にサポートすることが可能です。検査結果の数値を良くすることだけがゴールではなく、患者さんが自分の力で生活できるよう、またはサポートを受けながら生活を維持できるよう、医療とケアの両輪で支える病院を目指しています。


Interview –予防から在宅ケアまで支える地域包括ケアの実現
私たちの病院は、「病気になってから治療を受ける場所」だけではなく、病気になる前から健康を守り、予防に取り組む場所でありたいと考えています。特に、生活習慣病は地域の大きな課題です。これを早期に発見し、生活の中で適切にケアを行えば、急性期の治療が必要になった場合でも、侵襲の少ない治療で済み、短期間で回復できる可能性が高まります。
「病院の前(予防)」「病院での治療」「病院の後(回復期、在宅ケア)」というすべての段階を守る体制を作ることが、私たちの掲げる地域包括ケアの理念です。
もちろん、こうした取り組みは病院単独で実現できるものではありません。益田市や保健所、近隣の医療機関、さらには地域住民の皆さまと連携し、地域全体で取り組むことが必要不可欠です。連携体制をさらに強化し、病気の治療にとどまらず、地域で暮らす一人ひとりの生活そのものを支える仕組みを作りたいと考えています。


Interview –地域に溶け込み、人々が気軽に訪れる新しい病院の形を目指して
さらに、私たちが目指しているのは、病院を単に「病気になったときに訪れる場所」ではなく、日常生活の中で気軽に立ち寄れる、地域に溶け込んだ存在にすることです。健診や健康相談といった取り組みに対する心理的なハードルを下げ、地域の方々が自然に健康を意識できる環境を作りたいと考えています。
たとえば、病院の敷地内に庭やカフェを設置したり、ショッピングセンターやスーパーのような施設を併設することで、「ついでに病院に寄ってみよう」と思えるような場所にしたいと思っています。特に子育て中の方など、日々忙しく過ごしている方々にとっても便利な場所であれば、健診や健康相談への関心も高まり、病気の早期発見や予防につながると信じています。
健診は異常が見つかるかもしれないという不安から敬遠されることもありますが、病気を早く見つけることで、その後の治療を軽く済ませられる可能性が高くなります。だからこそ、健診や健康相談をもっと身近に感じてもらえるような工夫が必要だと考えています。 また、医療保険の枠を超えた取り組みとして、リハビリや栄養管理、健康相談を地域住民にオープンな形で提供することも検討しています。たとえば、ちょっとした相談事や悩みでも、病院が「まず話を聞いてくれる場所」だと思っていただければ、健診や医療への関心を自然に広げることができるでしょう。 私たちが目指すのは、「町の中の病院」という役割です。町の一部として、地域の暮らしに溶け込み、病院らしさにとらわれない新しい形の医療機関を作りたいと考えています。それはもちろん医療機関としての本来の役割を果たしつつ、人々が自然に足を運び、健康について意識し、支援を受けられる場所です。病院という枠を超えて、地域の暮らしを支え、健康を守るコミュニティの核となる存在へと進化していきたいと思っています。
こうした構想はまだ始まったばかりですが、地域の皆さまとともに、一歩ずつ実現に向けて進めていきたいと思っています。
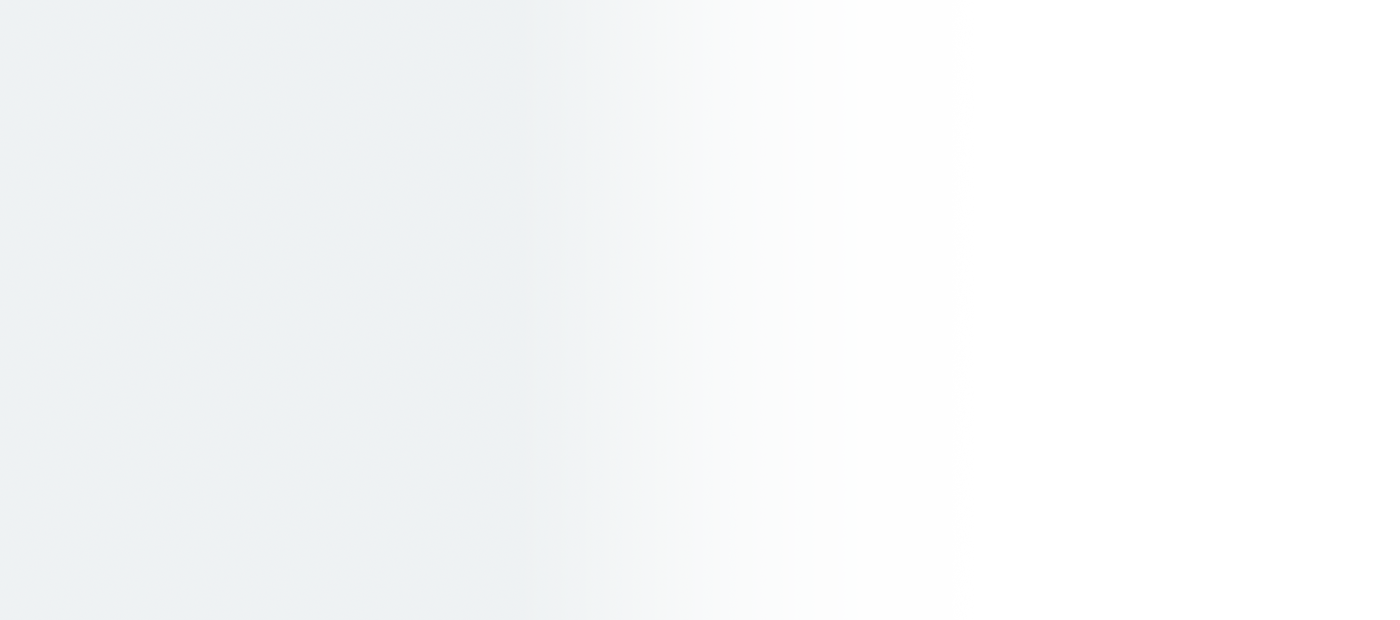

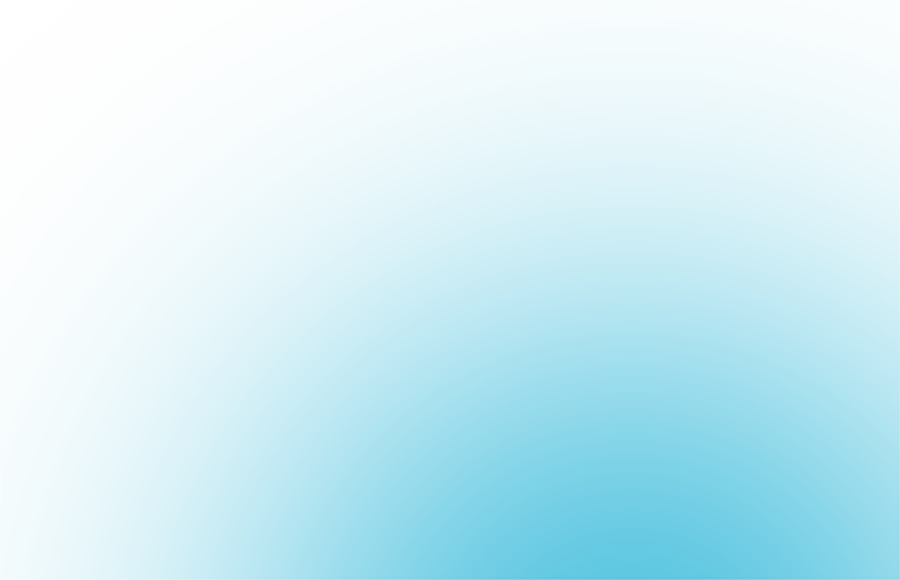
齊藤 洋司益田地域医療センター医師会病院長 院長
- 麻酔・蘇生学 / 疼痛学
- 2023年度 島根大学/医学部/特任教授
- 2018年度 島根大学/学術研究院医学・看護学系/教授
- 2009年度 島根大学/医学部/教授
- 2003年度 島根大学/医学部/教授
- 2000年度 島根医科大学/医学部/教授
- 1996年度 島根医科大学/医学部/助教授
- 1994年度 島根医科大学/医学部/講師