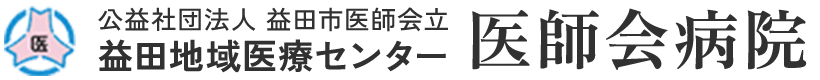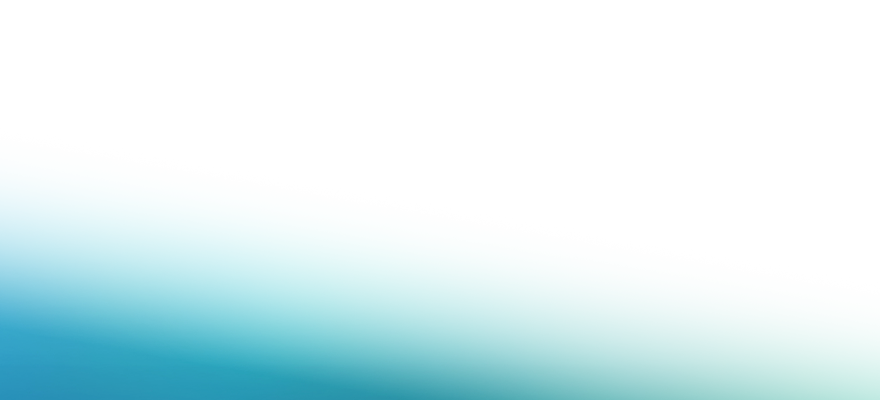

幼児期の運動について
【はじめに】
幼児期の神経系の発達は「6歳ごろまでに大人の約90%に達する」といわれており、この時期に多様な動きを行うことは、日常生活で必要な動き・防衛反応・将来的にスポーツに結び付く動きなどを獲得する上で、大変重要であると言われています。
しかし、日本における子どもの体力・運動能力について(東京オリンピックが開催された1964年以来、毎年文部科学省によって調査をされていますが)、1990年以降は低い水準が続いていると問題視されています。このことは、単に「体力・運動能力が低い」という問題に留まらず、「意欲」「集中力」「積極性」「自己統制力」「社会性」といった、認知的機能の働きにも悪影響を起こすことが明らかになっています。
この要因としては、近年の社会環境や生活様式の変化に伴い、体を動かす機会が減ってきていることが主に挙げられます。また、本年においては、新型コロナウイルス蔓延の影響により、世間では「例年と比べ体を動かす機会がより一層減っている」と心配の声が上がってきています。これを懸念して、メディアにおいては、多種多様な運動や遊びの紹介が放映されているのを、ここ数ヵ月で大変多く見掛けます。そうした中「子どもたちにとって、どの運動(遊び)を選び、実際に行なえば良いかわからない」というご意見をお持ちの方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、上記を踏まえ、「幼児期の運動」について、文部科学省により策定された「幼児期運動指針」をもとに紹介をしていこうと思います。
【「幼児期運動指針」の骨子】
- 指針の骨子1.「毎日、合計60分以上、楽しく体を動かす」その推進に当たっては、次の3点が重要です。
- 指針の骨子2.「多様な動きが経験できるように様々な遊びを取り入れること」
- 指針の骨子3.「楽しく体を動かす時間を確保すること」
- 指針の骨子4.「発達の特性に応じた遊びを提供すること」
出典:「東京大学名誉教授 小林寛道、2014」
【多様な動きを経験するには?】
以下に示す、基本的な動きをより多く獲得していくことが大切です。運動(遊び)の中で、これらの要素が取り込まれているかを意識して、多くの動きを経験できるように、子どもと話し合いながら工夫をしていきましょう。



出典:「文部科学省、2012」
【動きの発達について】
(1)3歳から4歳ごろ
基本的な動きが未熟な初期の段階から、次第に動き方が上手になっていく時期です。
「体のバランスをとる動き」や「体を移動する動き」を経験させていきましょう。
(2)4歳から5歳ごろ
それまでに経験した基本的な動きが定着し始める時期です。
「用具などを操作する動き」を経験させていきましょう。
(3)5歳から6歳ごろ
無駄な動きや力みなどの過剰な動きが少なくなり、動き方が上手になっていく時期です。
基本的な動きを組み合わせた動きにも取り組みながら、「体のバランスをとる動き」「体を移動する動き」「用具などを操作する動き」をより滑らかに遂行できるようになることが期待されます。
【運動(あそび)の工夫の例 ~「こおりおに」~】
「こおりおに」は、鬼にタッチをされると氷のように固まり動けなくなりますが、固まった者が仲間にタッチをされると、氷が解け再び動けるようになる鬼ごっこです。この「タッチをされると氷が解ける」の「タッチ」の部分を、別のものへ変更してみましょう。例えば「『凍っている者の背中を仲間が馬跳びをする』と氷が解ける」としてみます。こうすることで、楽しみながら様々な動きを経験できるようになります。また、「鬼」も「逃げる方」も走る方法を変更するのも良いでしょう。例えば、横向きで走る・片脚ケンケン・スキップで行うなどが挙げられます。
通常の鬼ごっこよりもルールがやや複雑になるため、5歳ごろより楽しめる運動(遊び)になると思います。
【運動(遊び)時の注意点】
- 幼児期は同じ年齢であってもその成長は個人差が大きいので、一人ひとりの発達に応じた援助を行っていきましょう。
- 保護者が必要に応じて手を添えたり、見守ったりして安全を確保しましょう。それとともに、遊具や用具の安全な使い方や、周辺の状況に気付かせるなど、安全に対する配慮をしましょう。
- 運動の前後・運動の合間で水分等を適切に摂取しましょう。また、適度に休憩を入れたり、体調に応じて運動量を調整するなど負荷が過度にならないように注意をしましょう。
【おわりに】
特に幼児期においては、色々なことに興味を持つ時期で、また子ども自身経験が少ないため危険に対する認識も低い時期でもあり、運動(遊び)時は常にケガなどの危険と隣り合わせにあると感じております。子どもの運動(遊び)を安全に行うためには、必ず保護者が同伴し、危険の箇所に気付かせてあげたり、安全に導くような声かけが必要と考えます。
今回紹介した内容を参考にしていただき、子ども達との運動(遊び)に少しでも取り入れていただければと思います。そして、楽しく継続していくには、「大人も楽しむ」ことが大切と考えております。周りの子と比べ過ぎず、その子自身の成長を褒めながら進めていただければ嬉しく思います。
参考資料・文献
文部科学省(2012).幼児期運動指針
日本発育発達学会編(2014)幼児期運動指針実践ガイド.杏林書院
-
2025年
-
2024年
-
2023年
-
2022年
-
2021年
-
2020年